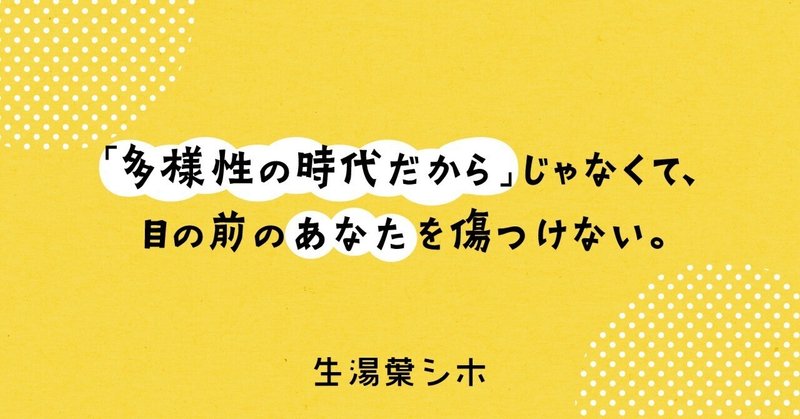
多様性に配慮しすぎて、なにも言えない。「関わらない」が安全策なのだろうか?
ライターの生湯葉シホさんに、「多様性が叫ばれる現代では、“関わらない”がいちばんの安全策なのだろうか?」というテーマで寄稿いただきました。
こんにちは、ライターの生湯葉シホといいます。私はふだん、人文系の研究者の方からアーティスト、個人商店を営む方など、いろいろなお仕事の方にインタビューをさせていただいたり、エッセイを書いたりしています。
今回、サイボウズさんから「多様性が叫ばれる時代、他者には『なにも言わない・なにもしない』のが安全なんだろうか?」というテーマをいただきました。
たしかに自分のまわりでも、「最近『〇〇』という言葉が簡単に使えなくなって、代わりの言葉に悩んでるんだよね」とか、「後輩の仕事への姿勢に納得がいかないんだけど、『多様性の時代』だから口出しちゃだめなのかな……」という悩みはよく聞きます。
私自身の人生経験・会社員経験はとても乏しいのですが……これまでに関わったいろいろな方の言葉や本などから言葉をお借りしつつ、このテーマについて、最近自分が考えていることを書いてみたいと思います。
先に結論から言うと、「多様性の時代だから、余計なことは言わず関わらないのがいい」というスタンスは一見やさしいようでいて、とてもつめたい態度なのではないか、と私は感じています。
「多様性」という言葉の使い方を、まず再点検したい
そもそも私は、「多様性」という言葉の使い方そのものに注意深くありたいと思っています。
もちろん、言葉自体が悪い、とは思いません。たとえばある組織において、管理職に就いている人たちのジェンダーバランスがあきらかに偏っているとき、「多様性のない組織だ」という批判が出るのは当然のことのように思います。
けれど、私たちがもっと大づかみに「(ある集団には)多様性がある/ない」という話をしだすとき、私たちの存在は地に足のついた実生活から離れ、もっと上の視点から集団を傍観し、ジャッジしているような感覚になっていないだろうか、と思うのです。
たとえば以前、「多様性」を学ぶための研修の一環として、発達障害のある人を招き、所定の期間だけチームに参加してもらうという取り組みをしていた組織の話を仕事で聞いたことがあります。
「『発達障害のある人』の視点が入ったことで、それぞれの違いをポジティブに捉えられ、多様な働き方を知ることができました」という研修の参加者の感想を耳にしたとき、違和感を覚えました。
当たり前だけれど、発達障害とひと言でいってもさまざまな障害があるし、その特性ってばらばらですよね。しかも、同じ障害のある人なら同じことが苦手(あるいは得意)とも限りません。
それなのに、たった数時間、数日の対話でその属性の人全体を「理解」したかのように考えてしまうのは、言葉を選ばずに言えば、傲慢ではないかと感じました。
ひとつのチームに、似通った属性だけではない、多様な人々が集まっていることはたしかにとても大切です。けれどこの例のように、「多様性がある」「多様性について一度学んだ」から、うちのチームはOK」と考えはじめると、いろいろなすれ違いが起きてしまうように思います。
「人それぞれ」で対話を避けることのつめたさ
「多様性の時代だから、なにを言ったらNGになるかわからない」と私たちがついおよび腰になってしまうとき、あたかも目の前のひとりの人が「多様性」を代表する人であるかのように感じてはいないでしょうか。
自分が若いころはふつうに通じた冗談だけれど、いまは口にしちゃいけないかもしれない(なぜならいまは「多様性の時代」だから)。話の流れでパートナーの有無を尋ねてしまったけれど、ハラスメントだと思われたかもしれない(なぜならいまは「多様性の時代」だから)……というように。
でも実際には、多様性を代表する「多様性さん」みたいな人はどこにも存在せず、ただ、さまざまな属性をもったひとりの人がいるだけです。だからほんとうなら、考えるべきは「多様性の時代的にOKかNGか」ではなく、目の前のこの人を傷つけてしまうかどうか、です。
ひとつ、自分のなかですごく印象に残っている言葉があります。社会的孤立・孤独や地域のネットワークについて研究されている、社会学者の石田光規さんという方の言葉です。
石田さんは、集団的な社会から個を尊重する社会への転換はよい変化をもたらした一方で、いまの社会では「相手の考えや行動を否定してはいけない」という前提ばかりが独り歩きしている、といいます。そんなシーンで重宝されるのが、「人それぞれ」という言葉です。
石田さんの著書から、すこし引用します。
私たちは、コミュニケーションの正解が見えないなか、相手の感情を損なう表現を避けつつ、その場を穏便にやり過ごすよう求められているのです。このような場で重宝されるのが「人それぞれ」という表現、または立ち位置です。「人それぞれ」という言葉は、相手の意向を損なわずに受容するという難題に対して、最適解を提供してくれます。
相手の考え方に違和感をもったとしても、「人それぞれ」と言っておけば、ひとまず対立を回避して、その場を取り繕うことができます。「べき論」を使って、規範を押しつけてくる人よりも、「人それぞれ」と言って、相手を受け入れてくれる人のほうが好まれるでしょう。私たちは「人それぞれ」という言葉を使うことで、さまざまな場を穏便にやり過ごしているのです。
(『「人それぞれ」がさみしい ――「やさしく・冷たい」人間関係を考える』より)
この「人それぞれ」と「多様性」は、とても使われ方が似ていると思います。どちらも「それを理由にすれば自分の正当性が担保される」「ここまではいちど考えたから、ここから先はいまは考えなくてOK」みたいな感じのマジックワードとして使われがちではないでしょうか。
けれど前に書いたとおり、実際に考えるべきは、目の前の他者が自分の言葉やふるまいをどう受けとるか、であるはずです。
「チェックリストにしたい欲求」を手放す
じゃあ、価値観が違う相手と関わろうとしたときに、自分の言葉が相手を傷つけてしまう可能性をどうやって判断すればいいの? とたぶんこれを読んでいる方は思われたと思います。
なんなら、相手を傷つけてしまう可能性のある言葉やシチュエーションをチェックリスト的にまとめて知りたい、と感じた方もいるかもしれません。
でも、ちょっと意地悪に聞こえるかもしれませんが、「チェックリストとして確認したい」という欲求を手放すところから関わりがはじまるんじゃないか、とあえて言いたいです。
もちろん、企業の採用面接や1on1ミーティングといったオフィシャルな場、教師と学生のように立場の強弱がある場では、人の尊厳に関わる「言うべきではない(尋ねてはいけない)こと」は存在するし、それをルール化することは明確に必要だと思います。
けれど、そういった場から離れたもうすこしゆるやかな個と個の関わりにおいて、「この言葉を言ったらNG」という絶対的な指標は設けないほうがいいと個人的には思っています。
卑近な例を挙げるなら、私は基本的には初対面の方の配偶者を「パートナー」と呼ぶほうだけれど、ある知人の前でその人の配偶者について話すときは「旦那さん」と言います。
その知人が「旦那」という呼び方に愛着を持っていて、なおかつ周囲にそう呼ばれることにも抵抗がないと話しているからです(ほかにも、「ワイフ」呼びが定着している知人の前ではそう呼んだりもします)。
この人の配偶者のことは「お連れ合い」と呼ぼうと決めている相手もいるし、もうちょっとラフに「彼氏」と呼ぶこともあります。
人の容姿に言及していいかどうかわからない、というのもよく話題になるトピックです。私自身は「髪切りました?」程度であればだいたい誰にでも言うし、「その靴素敵ですね」みたいなこともわりと言うほうです。
ただ、もし自分が組織の管理職に就いていたとしたら、「香水いつもと違います?」という質問は、その場で思い浮かんだとしても、関係の濃淡によって言う相手と言わない相手がいるかもしれません(私なら、おそらく部下やよっぽど親しくない相手には言わないことが多いと思います)。
めちゃくちゃ曖昧じゃん、って感じですよね。でもほんとうに、そのくらい曖昧でフレキシブルに捉えるべきじゃないかなと思うのです。「言っちゃいけないこと」「人を傷つけること」は、お互いの関係や立場、シチュエーション、会話の文脈によって目まぐるしく変わるはずだからです。
「その1人を1万人に変えてしまわない」
それから実際、私たちが直面したときにいちばん迷うのは、助言や手助けが必要そう(に自分からは見えている)相手に対して言葉をかけるかどうか、かもしれません。
お節介とか失礼だと思われるかもしれないし、相手に怒られてしまう可能性すらある。それならなにもしないほうが……と、街なかで見かけた高齢者や妊婦の人を見て見ぬふりした経験のある人はきっと少なくないはずです。
自分自身、家の近隣で虐待が疑われる様子の子どもを見かけて、児童相談所に相談しようか迷いに迷ったことがあります。
結局、児相に報告し、子どもが保護されるところを見守ったのですが、その前後の対応も含めて、過剰な心配だったのでは? とか、その子自身を追い詰めることになったのでは? と当時かなり悩みました。同じようなことがもしもまた身近で起きたら、その経験を思い出し、どうすべきか余計に悩んでしまうかもしれない。
そういうときに決まって思い出すのが、以前お仕事でお会いした、志村季世恵さんという方の言葉です。志村さんは、視覚障害者や聴覚障害者のアテンドが活躍しているソーシャルエンターテインメント施設、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」などのプロデューサーをされています。
手助けを必要としているかもしれない人に街なかで出会ったとき、声をかけることをどうしてもためらってしまう……という悩みをインタビューで伝えたとき、志村さんはこう答えてくれました。
手助けが必要そうな人に声をかけて「大丈夫です」って断られちゃうことはたしかにありますよね。そういうときってショックだと思います。でも、困っている人が仮に1万人いるとして、あなたに「大丈夫」って言ったのはそのうちの1人だけなんですよ。だから、その1人を頭のなかで1万人に変えてしまわないことが大事なんじゃないかな。
私は自分自身、子育てしていたときに本当にいろんな人たちが電車のなかや街なかで声をかけてくれて、そのおかげで孤独を感じずにいられたという経験があります。だから私も「大丈夫」って断られることはあるけれど、それでも毎回困っていそうな人がいたら声をかけることにしています。
(Webメディア「こここ」インタビュー「『助けて』とお互いに言い合えるのが、成熟した社会。ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表 志村季世恵さん」より)
「その1人を頭のなかで1万人に変えてしまわない」という言葉は、聞いた瞬間かなり衝撃的だったのでよく覚えています。ああほんとうにそうだ、私は自分にネガティブな感情が残った1件のケースを「そのパターン全部」に変えて捉えようとしてしまうことが多すぎる、と大いに反省したのでした。
「関わらないでおこう」の引力はあまりに強いけれど
だから、自分の体力と気力がゆるす範囲で、関わりたい他者とはできる限り関わってみる。そこで感じたことを、過剰に「応用」しようとはせず、「そのときのその人」とのコミュニケーションの結果として考える。
そのうえで、「この言葉は差別的な由来を持っていると学んだから、よっぽどのことがない限り使わないでおこう」とか「失礼かもしれないけれど、この人にはこれを聞いてみよう。もし傷つけてしまったら真摯に謝ろう」という経験を積み重ねながら、すこしずつ自分のベーシックなコミュニケーションの軌道を変えていく。
……言葉にするとあまりにシンプルだし理想論的すぎるとも思うのですが、そういうことの繰り返しでしか「関わらないのが安全」という、ミニマルで便利だけれどつめたい考えからは離れられないんじゃないでしょうか。
個と個の関わりにおいて厳密な唯一のルールを設けない、というのはたぶん、自分と周囲の人の肩の力をすこし抜くと同時に、心地いい緊張感を持続させるような考え方ではないかと思っています。
「これを言ったら即NG」というセンサーを常に頭のなかにおいて生活するのはかなり苦しいし、人を簡単に見限ってしまう理由にもなります。
それに、自分はそのNGラインをいちど乗り越えた、という感覚は、「かつてはそれをごくふつうに口にしていた自分」をなかったことにしてしまう考えとすごく相性がいいと思うのです。「自分はヤバいことを言ってない側だからセーフ」と感じはじめると、人はほんとうにいつでも簡単に人を傷つけるものだと思います。
ここまで書きながら、自分がこれまでにした失言やあきらかに失礼だったコミュニケーション、そして自分の想像の及ばないところで傷つけてしまったであろう人たちのことを考えて、そわそわと落ち着かない気持ちになってきました。
人と関わるのは私自身、やっぱりめちゃくちゃこわいし、「だから関わらないでおこう」という考えが持つ引力はあまりに強いとも思います。けれど、少なくともこの不安を抱えながら私はもうしばらくやっていくので、どうにか一緒にがんばりましょう、と言いたいです。
※この記事は、サイボウズ式特集「多様性、なんで避けてしまうんだろう?」の連載記事として2023年3月30日に公開されたものです。
執筆:生湯葉シホ 企画・編集:深水麻初

