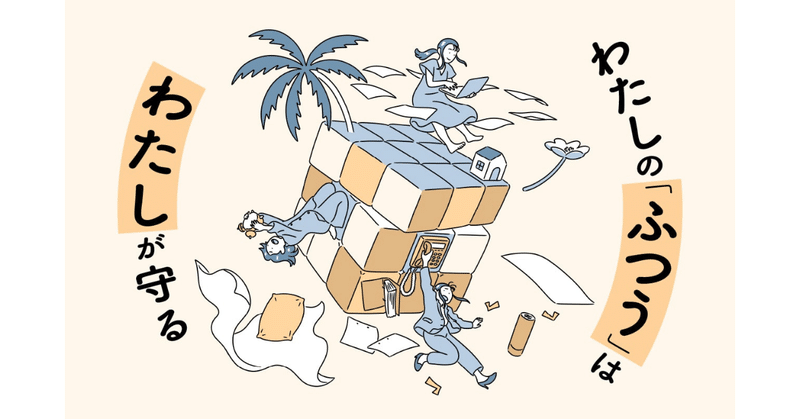
「なんで、ふつうにできないの?」そう浴びせられてきた人たちへ。
本特集『「ふつう」を、問い直してみよう。』では、サイボウズ式ブックスから発売された書籍『山の上のパン屋に人が集まるわけ』をきっかけに、さまざまな人と一緒に「ふつう」について考えていきます。
今回は、フリーライター・いしかわゆきさんに、「自分なりのふつう」の守り方についてコラムを執筆していただきました。
「なんで、ふつうにできないの?」
という言葉を、何度人生で浴びせられただろう。何度頭のなかで反芻しただろう。母の説教を、クライアントの怒号を、右から左に聞き流しながら、「そんなの、わたしが1番知りたいんだが〜!」と憤っていた。
「ふつう」って何やねん。どうしたらそこに到達できるのよ。散々悩んで、試行錯誤した挙句、とうとうわたしは「ふつう」になれず、会社を辞めて、フリーランスのライターとして働きはじめてから4年が過ぎた。
いまのわたしは、世間の「ふつう」にポイと匙を投げている。「なんでふつうにできないの?」そんなことを言う人はもう、まわりには残っていない。
遅刻しないように頑張らなくちゃ。
変な人だと思われないように口をつぐまなくちゃ。
めでたい場だから楽しそうに振る舞わなくちゃ。
そういうのを一切捨ててしまったわたしは、ずいぶんと「ふつう」から遠い場所に来てしまったような気がする。
でもわたしは、そんなわたしのことを嫌いじゃない。
「ふつう」とは「努力」のうえに成り立つもの
ちょっとだけ自分語りをしてみたい。
昔から「変わってるね」と言われることが多かった。当時は褒め言葉として受け取っていたが、今思えば要するに「アンタ、ズレてんね」ということだと思う。
もともと、小さいころからひとりで絵を描いたり、本を読んだりして過ごすことが好きで、ひどく内向的な性格の持ち主だった。言葉を選ばずに言えば、他人にマジで興味がなかったのである(どおん)。
だから、休み時間は机に向かって過ごすことが多かった。友だちは大していなかったが、「4人グループを作ってください!」と言われたらアタフタするぐらいで、別に困りはしなかった。
しかし、そんなわたしに転機が訪れる。
中学2年生で渡米することになったわたしは、厳しい現実に直面することになった。いかんせん言葉がチンプンカンプンなので、何も喋らずにいたら、ガチで「ぼっち」になったのである。
自ら関わろうとしない限り、まわりの人はスルーしていくばかりで、授業はおろか、普段の学校生活でも何も理解できないまま、同級生から後れを取っていく生活が始まった。トイレでサンドイッチを頬張りながら、「日本に帰りたい……」と何度も思った。
もしや、このアメリカという地では、人と関わらなくては死ぬのでは!? そう危機感を覚えたわたしは、まずはじめに、顔の筋肉を動かして人の良さそうな笑顔を作ることを覚えた。
会話の内容がよくわからなくても、声を出して笑っておく。まわりの人が興味のありそうなトピックを勉強して、ネタをストックする。行きたくなくても、誘いには乗っかっておく。そうすると、何だか「ふつう」に人とコミュニケーションを取れているような気がした。
しかし、そうやってやり過ごしたあとは、いつもぐったりと疲れ、ベッドで死んだように眠ることになった。全然大丈夫ではなかった。だんだんと、自分自身と、もうひとりの自分が乖離していくのを感じる。「ふつう」に馴染むには、努力が必要不可欠なのだと知った。
わたしの「ふつう」は、まわりが守ってくれていた
さらに、大学生になると、今度は別の「ふつう」にも苦しめられることになる。
ラク単(ラクに単位が取れる)と言われているはずの授業を落とし、朝7:00からのカフェバイトは毎日寝坊、コールセンターのバイトは3日間でクビになる。高校まで、無遅刻無欠席を貫いていたわたしは大混乱した。度重なる遅刻と欠席と物忘れ。一体何が起きているんだ!?
答えはシンプルである。ぜんぶ、両親がやってくれていたのだ。
「忘れ物はない?」「あと5分で出る時間じゃない?」「駅まで送ろうか?」
そんな声掛けや行動が日常にあったからこそ、わたしの生活は成り立っていたのだ。実家を出て初めて、わたしの「ふつう」は、まわりの手厚いサポートによってかろうじて守られていたのだと愕然とした。人はひとりでは生きていけないとはよく言うが、わたしも全然ひとりじゃ生きていなかったのだ。
そして言わずもがな、ルールを守れない者に、社会はひどく冷たい。
遅刻を繰り返し、何度シフトに入ってもメニューを覚えることができなかったバイト先では、怖い先輩の顔しか見たことがなかったし、相変わらず人とうまく喋れないので友だちもいなかった。
その後も、スケジュール管理ができないためにESの〆切を守れず、方向音痴で面接に行けず、就活もことごとく失敗。
かろうじて就職した中小企業では営業職に就いたが、起きれなさすぎてベッドのなかから勤怠報告の電話をする、電車を逆走してアポに遅刻する、物覚えが悪すぎて商品をうまく説明できずで、わたしの自己肯定感は地に落ちていった。
人と関わることができないだけではなく、社会の規律に沿って動くことすらできない。
「早く起きたいなら、早く寝ればいい」とか、「忘れものは前日にチェックしよう」とか、「時間を逆算して早く現地に着いておこう」とか、そういうアドバイスも聞き飽きた。
アドバイスをした者は、それでもうまくできないわたしに対して、やっぱりこう言った。
「なんで、ふつうにできないの?」と。
わかんないよそんなん。でも、なんか知らないけどできないんだよ。
「世の中のふつうになれない」。その事実だけがただ、わたしを悩ませるばかりだった。
環境を変えてみたら、「ふつう」が壊れた。
「ふつう」についての考えが変わったきっかけは、転職だった。
新卒で入った会社で1年半ほど営業をしたのち、広告代理店に入社した。入社早々、深夜まで会社に残って仕事をする日々が始まったのだが、あるとき気付いてしまった。
うちのチームメンバー、誰も朝に出社してなくね??
それもそのはず、シンプルに遅くまで残業しているのだから、誰も起きられないのである。昼ごろに何食わぬ顔で「オハヨウゴザイマース」と出社しても、誰も責める者はいないのだ。完全に暗黙の了解である。
ヤバい職場だと思うだろうか。ところがどっこい、この環境こそが、わたしにとっては大変心地がよかったのである。
わたしは時間を守るのは苦手だが、ひとつのことにガッと集中するのは得意なので、一度のめり込んだら、やり切るまでとことん机に向かうことができる。
だから、この「朝に起きる必要がなく、夜は何時まででも働ける」環境は、最高に働きやすかったのだ。
さらに、前職の営業職と違って、人とガッツリ関わる必要もないので、ひたすらパソコンに向かって作業していればいい、というのも大変ありがたかった。
仕事を変えたことで、仕事量は何倍にも膨れ上がったが、代わりにわたしの「ふつうじゃない部分」が露呈しなくなった。革命が起きたのである。
その後は、より自分にフィットした環境を求めて、最終的にフリーランスに転向することになるのだが。
自分が動き、半径5メートルの世界を変える
さまざまな環境を経たうえで噛み締めていることが2つある。
ひとつめは、環境によって、「ふつうか否か」というのは変わるということ。
1社目では、「5分前行動」が鉄則で、時間を破ることなど言語道断であった。でも、次の会社では、必要な仕事さえできていれば、朝起きなくとも責められず、多少の遅刻は許された。
また、1社目では、電話や対面でのコミュニケーションが求められた。でも、次の会社では、メールやチャットでのコミュニケーションが主で、逆に電話は鬱陶しがられた。
環境が変わると、マイナスだと思っていた自分の性質が、プラスに働くことだってある。
たとえば、わたしの「過集中」という性質は、営業では活きなかったし、合間に会議が挟まれる会社ではかえって邪魔になっていた。でも、フリーランスになると、自分でスケジュールを組み立てることができるので、「5時間で原稿を書き上げる」という芸当ができるようになった。
「衝動的に何かがやりたくなる」という性質も、会社ではふらふらと立ち上がってどこかに行ってしまって落ち着かなかったが、フリーランスになってからは、衝動的に生んだたくさんの発信が、多くの仕事へと繋がった。
ふたつめは、環境というのは、自分でいくらでも変えていけるということ。
社会人であれば、転職や部署移動でもいいし、まわりの人に相談してみるのでもいい。
たとえば、
「電話が苦手なのでテキストで送ってもらってもいいですか?」
「壁際が集中できるので、席を移動したいです」
「できれば前日にリマインドをもらえたら嬉しいです」
……などは、わたしが会社員のころによくお願いしていたことだ。
人はそれぞれ、苦手なことも得意なことも違う。相手が苦手だけど、自分が得意なことを率先してやれば、代わりに自分の苦手なことを快く引き受けてくれるはずだ。
自分の苦手を押し殺しながら生きると、「ふつうじゃない」という烙印を押されてしまう。でも、自ら弱みを開示して、強みを発揮できるように環境を変えていけば、どんどん息がしやすくなっていく。
自分にとっての「ふつう」を守るためには、自分が世界に合わせるのではなく、自らが動いて半径5メートル範囲の世界を変えていくことが大切なのだ。
「ふつう」とは一体何なのか
さて、これまでわたしが苦しめられつづけてきた「ふつう」とは一体何だったのか。
わたしは、「ちょっとだけ数が多いこと」が世間で「ふつう」と呼ばれているものの正体なのだと思う。
しかも、「みんな=大多数」と呼ばれるものは、実はそんなに数が多くなくて、せいぜい自分のまわりの友だち3人ぐらいだろう。3人が「A」と言ったら、「A」が「ふつう」のように感じてしまうのだ。
たとえば、自分のまわりの友だち3人が就職していたら、「会社で働くのがふつうなんだな」と思うし、みんなが結婚していたら、「結婚するのがふつうなのかなぁ」と思えてくる。
そんな、「A」が大多数のなかで、異端となる「B」を信じるために必要なのは「あなたとわたしは住んでいる国が違うのね」という割切り力と、自分の「ふつう」を守ろうとする信念だ。
これらを大切にするためには、「すべての人に認めてもらう」という欲求を捨てたほうがいい。現にわたしは、「遅刻癖があり」「いろいろ忘れてしまい」「だらしない」人間なので、さまざまな人が去っていってしまった。失ったものは多いと思う。
でも、その結果いまは、1時間の遅刻をやらかしても、「遅刻してくれたおかげで、本を1冊読み終えたよ。ありがとう!」と嫌味でも何でもなく言ってくれるような徳の高い人ばかりがまわりにいてくれている。
以前、なぜこんなポンコツにやさしくしてくれるのかと尋ねたことがあるが、「一緒にいて楽しいから」と返してくれた。
いいところも悪いところも含めて、素直に自分をさらけ出し、「それがいい」と認めてくれる人たちと一緒に過ごせば、あなたの「ふつう」は守られるのだ。
それに、無理をして背伸びをして作った「偽りの自分」で得た関係性など、あっという間に崩れていくし、「偽りの自分」を好きになってくれた人とは、絶対に合わないはずだから、お互いのためにも一緒にいないほうがいいと思う。
わたしはこれを、「自分だけの城を築く」と表現している。
そこに住むのは、苦手なことも、弱いところも含めて、自分のことを認めてくれる人たち。「それはおかしい」と石を投げるような人がいるのなら、自分も相手も否定せずに、そっと自分の城から追い出すのみだ。
価値観はそれぞれ違うから、「ふつう」だと信じているものはみんなそれぞれ違うはず。「あなたにとってはそれが『ふつう』かもしれないけど、ここでは違うんだよ」と言えるような、心理的安全性が保たれた場所を築いていこう。
わたしもそうだったが、「ふつうになりたい」と願う人は、自分を押し込めてまわりに合わせる努力をする。でも、そうじゃない。自分の「ふつう」を大切にするために、自分の世界を変えていくんだ。
今のわたしは、1時間遅刻しても爆笑してくれる友人と、「何だかんだで書き上げてくれると信じています」と言ってくれるクライアントに囲まれた、小さくとも心地のいい世界で生きている。
「なんで、ふつうにできないの?」そう浴びせられてきた人たちへ。
「むしろ、これがわたしのふつうだが?」と胸を張って生きていけるような城を築いてください。大丈夫。あなたの「ふつう」はおかしくないよ。
※この記事は、サイボウズ式特集『「ふつう」を、問い直してみよう。』の連載記事として2023年8月29日に公開されたものです。
企画・編集:あかしゆか/執筆:いしかわゆき/イラスト:芦野公平/デザイン:駒井和彬
👇サイボウズ式特集『「ふつう」を、問い直してみよう。』はこちら!

